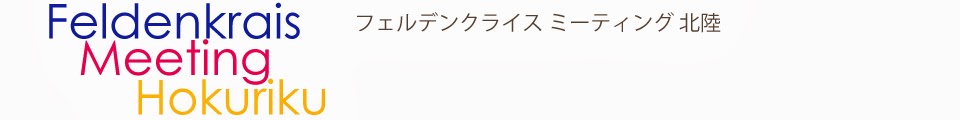しかし、同じ温度、同じ時間、同じ豆で淹れていても味に違いが起きる。
これは当たり前であり、この淹れ方では場の温度や湿度、何より飲む人のコンディションなどが視野から外れている。何よりも、豆の反応を肌で感じなければ、その日、その場での最も美味しいコーヒーに至ることは難しい。
最初に投入するお湯は豆を中央から目覚めさせる。
目覚めには強さや速度があり、泡や立ち上る香りから解るときがある。
挽いた豆は逆円錐状の深さを持っており、その広がりはお湯を表面に落とす塊の大きさや強さで変わる。
続けて入れるお湯は、下の容器に落としていくことを意識しながらもそのコーヒー豆の持つ力を散逸させない加減を要求され、落ちるお湯が呼吸で言うところの吐く行為であれば、入れるお湯が吸う行為であり、常にそこに心地よい呼吸をもたらすことで維持されるものがある。
終わりを計るのは最も多くの感覚を要し、その容器にたまったコーヒーの密度と豆から絞り出される最後の味の雰囲気と飲む人が要求する味の重さ、軽さの中で引き際が導かれる。
飲み方によってはさしたる違いを感じないレベルの話であるとは思う。
しかし、コーヒーの味だけを見ていると全く見落としてしまうことが、
淹れることと飲むことの渾然一体とした時間の中に生き生きと存在しており、
コーヒー飲料を得る作業というよりは、コーヒー豆にお湯をたらす中で広がる世界を得ることが、子供の砂場の遊びのような輝きを放つのだ。
この輝きこそ、生きることの実感であり、フェルデンクライスで私が追求している何かだと思う。